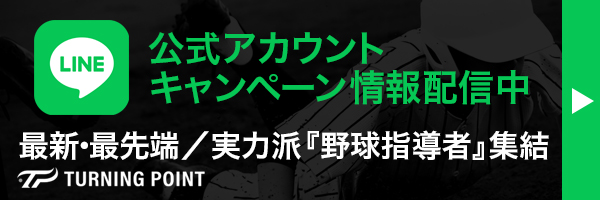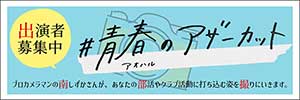日本に2度目のラグビーW杯はやってくるのか 2035年に照準も…大会は巨額ビジネス化、WRとの“綱引き”に

対抗馬にはスペイン、イタリア、英国&アイルランド
JRFU側にも確認を取ると、「なるべく早い開催を期待している」(JRFU関係者)という理由で39年の選択肢よりも35年開催を優先させている。35年の開催を希望している日本に対して、WRは39年にも触れることで、2つの開催年という含みを持たせている。35年か39年なのか。その背景にはWRが変更した開催国選定方法も影響しているようだ。
【注目】日本最速ランナーが持つ「食」の意識 知識を得たからわかる、脂分摂取は「ストレスにならない」――陸上中長距離・田中希実選手(W-ANS ACADEMYへ)
従来は、開催希望協会(国・地域)が大会の理念、プラン、収益目標などを競い合い、最終的にWR理事会での投票で開催国が選考されてきた。だが、現在既に開催国が確定している2027年、31年大会からは、新たな考え方に基づいた選定が行われている。ロビンソン会長は、こう説明している。
「WRは、従来の4年に一度開催国を決めるために協会同士が競争するやり方を辞めることにしました。長期的に、財政面でもしっかりと検討して、新たな市場を開拓出来るチャンスがあるかどうかを見極めていきます。その考え方に則り27年にオーストラリア、31年はアメリカが選ばれた。35年、39年のW杯も、どこで開催するのが財政的に意味があるのか、どこで選手がプレーするのがいいのかに基づいて決定されます」
前回の日本開催の選考でも、実は2015年のイングランド開催とワンセットで19年の日本が選ばれている。当時のWRでは、2011年大会の招致には敗れたものの、日本という“第3極”の存在は無視できない状況だった。そこで採用されたのが、収益性の高いイングランドで開催した後に未知数の日本で開催するという2大会同時選考だった。日本については、準備時間を長く持たせるべきだという意見も強く、15年ではなく19年開催へと票が流れた。現行方式は、WRでの投票という方式は変わらないが、2019年の選考過程にさらに運営能力、収益性なども精査して開催国が選定されていくことになる。WRの開催国選定プロセスからは、従来以上に収益性も含めて確実性のある開催国を選び、大会を成功させたいという強い意思が読み取ることが出来る。
このような選考方法も踏まえて、WRが35年、39年大会の開催国選定をより効果的で収益性の高いものにするために、バランスを考え、柔軟性を持ちながら進めようとしているのに対して、日本側はより早い開催を求めている。そのために、日本側も就任早々の新会長を含めたWR首脳陣とのW杯を題材にした話し合いを持ちたかったことも、このタイミングでの訪日が実現した理由でもあるはずだ。JRFUでは、年々薄れつつある2019年大会で得た様々なレガシーや収益、普及・強化の恩恵を、出来る限り早く取り戻したい。現在の協会首脳陣が次の日本大会の開幕の時にどこまで在職しているかは分からないが、少なくとも自分たちの在任中に再招致を実現させたいという思いもあるだろう。日本側はおそらく39年という可能性も考えながら「35年の男子、37年の女子」というセットを売り込み、WRは開催年に含みを持たせている。すでに、静かに「35年」と「35年ないし39年」という戦いは始まっている。
では、日本の対抗馬はどうだろうか。確定している31年大会以降の開催に意欲を示している国・地域について、ギルピンCEOはこう語っている。
「名前を挙げられるとすれば、スペイン、イタリアが公式に開催したいと表明して、英国とアイルランドが共催で関心を示している。他の協会でも関心を持っているところがある」
WRにとっては、過去に開催実績がなく、2月第2週現在世界ランキング18位のスペインのような国が開催に意欲を見せるのは歓迎出来る一方で、巨大化する大会をしっかりと運営出来るのか、そして期待される収益性を確保できるのかは重大なテーマになる。日本は19年大会で99%のチケット販売を達成して、6000億円を超える経済波及効果を生んだと報告されている。危惧された収益性でも一定の結果を出せている。その一方で、23年大会を開催したフランスや、再び手を挙げようとしている英国・アイルランドほどのラグビーの強固な地盤を持っていないことから、いまは伝統国と新興国の間に位置づけられていると考えるのが妥当だろう。2035年、39年の開催を考えると、WRが導入する2大会同時選考では、15年、19年同様に安定した収益性と開催能力が計算できる英国ベースの大会後に日本開催というシナリオがあってもおかしくない。ちなみに、注目される今後の開催国決定時期について同CEOは「2035年の開催国については、27年大会の開催前に決まると思う。なので7年、8年前から準備が出来ることになる」と説明している。
W杯を「開催能力」という側面から考えると地殻変動が起きていることも、今後の選考に影響がありそうだ。日本が19年大会で、伝統国以外、アジアでの初開催という価値に加えて、過去の大会で最多となる68億円の黒字を記録するなど収益性も残したこと、そして日本代表も初のベスト8進出なども含めてWR内でも評価を得た。だがその一方で、従来W杯を開催してきた常連国には陰りも見えてきている。
投票による日本との招致レースを制して2011年大会をホストしたニュージーランド(NZ)は、歴史的な第1回大会をオーストラリアと共催(決勝戦はNZ)するなど、代表チームの実力も含めて誰もが認めるラグビー大国だ。だが、開催国優勝を果たした11年大会の前から、これがNZで最後のW杯になるのではないか――という声は少なくなかった。2011年の時点で、W杯はすでに企業、政府などからの巨額の投資が求められる大会に膨れ上がり、同国の国内資本では十分に賄えない規模に達していたからだ。
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)