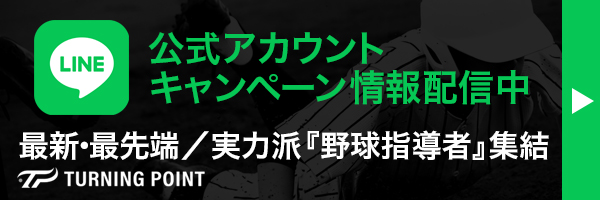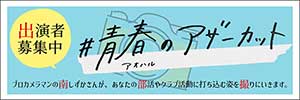指導論の記事一覧
-

プロテニス選手が福島で説いた、もう一歩頑張る練習「諦めることなく今できる全力を」
2019.07.27プロテニスプレーヤーの綿貫敬介(明治安田生命)が21日、福島県いわき市のテニスコート「ア・パース スタジアム」で行われた東北「夢」応援プログラムの「夢宣言イベント」に参加した。小学3年生から中学3年生まで少年少女14人を対象に約2時間のクリニックを開催。子供たちとの対面を楽しみにしていた綿貫はこの日、「試合で緊張したり、プレッシャーを感じる中で、もう一歩頑張るための練習」を伝えた。
-

行動に移せる子、移せない子の差 神野大地が安定を捨て、挑戦を続けられる理由
2019.07.215月のある日、神奈川・相模原市内の閑静な住宅街にある小学校に「山の神」がいた。東京五輪を目指す陸上長距離の神野大地(セルソース)だ。訪れたのは、LCA国際小学校。9月にマラソングランドチャンピオンシップ(MGC)を控え、多忙を極めるトップ選手が練習の合間を縫ってやって来たのは、なぜなのか。
-

「日本にも負けないはず」 西野朗を招聘したタイの英雄、母国サッカー発展への確信
2019.07.19前日本代表監督の西野朗氏がタイ代表監督のオファーを受けた背景には、ヴィタヤ・ラオハクル氏の後押しがあったとの報道があった。
-

ラグビー日本代表キャップ計197 箕内拓郎、小野澤宏時、菊谷崇が挑む新たな育成指導
2019.07.19コミュニケーション能力があり主体的に状況判断ができる人間を育てたい――。そんな思いから始まったラグビーアカデミーがある。それが「ブリングアップ(BU)ラグビーアカデミー」だ。
-

スポーツ英才教育の是非 元Jリーガーが指摘する「保護者が陥りやすい」愛情の罠とは
2019.07.06自分の息子に24時間体制でサッカーを徹底的に教え込み、バルセロナの選手にする! 元Jリーガーは、自分が過去に言い放った言葉を恥じていた。鹿児島実業高校で全国高校サッカー選手権の初優勝に貢献し、アビスパ福岡、横浜F・マリノス、大宮アルディージャといったプロチームで活躍した久永辰徳氏だ。
-

変わろう、野球 筒香嘉智の言葉「日本で使われている金属バットの弊害は大きい」
2019.07.02高校からプロ野球へ進んだ打者の多くが、プロ入り後にまず経験するのが、打球が思うように前に飛ばないことだという。プロ10年目のシーズンを送る横浜DeNAベイスターズの主砲・筒香嘉智外野手もその1人だった。今でこそ日本を代表する打者となったが、1軍に定着したのは2014年のこと。横浜高では通算69本塁打を記録し、“超高校級”とまで言われた男でも、1軍で打率3割、20本塁打を記録するまで5年を要した。
-

1分の「作戦タイム」で何ができるか? ラグビー元日本代表2人も驚いた小学生の可能性
2019.06.28ラグビー元日本代表の小野澤宏時氏と菊谷崇氏が27日、神奈川県・相模原市内のLCA国際小学校を訪れ、ラグビーの楽しさを伝えた。プロのコーチとして「ブリングアップラグビーアカデミー」を主宰する2人は、小学4、5、6年生にラグビーボールを使ったミニゲームを通じて、自由な発想と積極的なチームトークを奨励した。
-

子供に結果を求めたがる保護者たち 東京の保育園がスポーツで育てたい「本物の意欲」
2019.06.23今、東京から始まった新しい取り組みで保育の現場が変わるかもしれない。「幼児スポーツ教育プロジェクト」――。都内で16の保育園を運営する社会福祉法人「東京児童協会」が、株式会社「CRIACAO(クリアソン)」の協力を得て始めた保育園向けプログラム。「スポーツを通じて子どもたちの可能性を最大化する」をコンセプトに、昨年から始まった異色の試みだ。
-

元オリンピック選手が保育園児に教える 異色の“幼児スポーツ教育”挑戦のワケ
2019.06.22今、東京から始まった新しい取り組みで保育の現場が変わるかもしれない。「幼児スポーツ教育プロジェクト」――。都内で16の保育園を運営する社会福祉法人「東京児童協会」が、株式会社「CRIACAO(クリアソン)」の協力を得て始めた保育園向けプログラム。「スポーツを通じて子どもたちの可能性を最大化する」をコンセプトに、昨年から始まった異色の試みだ。特筆すべきは、スポーツ界のトップアスリートが実際に保育園で指導を行うということである。
-

変わろう、野球 筒香嘉智の言葉「勝つ為にやらされる野球になったら、それは不幸」
2019.05.27横浜DeNAベイスターズの主砲・筒香嘉智外野手は、プロ10年目を迎える今でも、子供の頃から変わらず持ち続けているものがある。それは「野球が大好き」という気持ちだ。ただ、ふと周りを見回してみると、好きで始めたはずの野球が、いつの間にか「やらされているもの」に変わってしまった人も多い。
-

日本の小学生は休めているのか ドイツで大切にされている連休中の「子供の時間」
2019.05.14日本では昔からよく言われている。誰でも知っている言葉のはずだ。しっかりと寝て、身体を休ませることが大事だと――。
-

「20人集まれば4~5人やりたがる」 子供がGKに憧れる“先進国”オランダと日本の違い
2019.05.03「オランダでは子供たちが20人くらい集まれば、必ず4~5人はGKをやりたがる。ブラジルじゃ、ありえないよね」――ハーフナー・ディド(元マツダ、名古屋グランパスエイトほか) オランダは伝統的に足もとの上手いGKを輩出してきた。今ではGKがビルドアップに加わるのは当たり前だが、時代を先駆けていたという見方もできる。
-

「文句を言ったら泣き出した」 外国人GKが30年前の日本で感じたミスを指摘しない習慣
2019.04.27ハーフナー・ディドが初めて来日してから、もう30年以上が経過した。今ではマツダ(現・サンフレッチェ広島)でプレーしていた頃に生まれた長男マイクのほうが有名になったが、エールディビジ(オランダ1部リーグ)で6シーズンもプレーしてきたGKが、1986年に日本のアマチュアリーグに参戦したのだ。その格差を考えても画期的なことだった。
-

変わろう、野球 筒香嘉智の言葉「子どもは大人の顔色を窺いながら野球をしている」
2019.04.22横浜DeNAベイスターズの主将であり主砲の筒香嘉智外野手。今季チームを21年ぶりの日本一に牽引するべく、日々の戦いに専念する大砲だが、オフには野球界の現状に危機感を抱き、未来ある子どもたちの可能性を守るべく、勇気ある発言を繰り返している。今年1月25日には日本外国特派員協会で会見し、約1時間に及ぶ質疑応答の中で真っ直ぐな意見をぶつけた。枠からはみ出ることを恐れない現役選手による発言は、野球界に一石を投じただけではなく、スポーツ庁の鈴木大地長官にも引用されている。
-

本当のミスとは「チャレンジしないこと」 日本で4クラブを率いた外国人監督の信念
2019.04.17ランコ・ポポヴィッチは、2009年の大分トリニータを皮切りに、FC町田ゼルビア、FC東京、セレッソ大阪と4つのJリーグクラブを指揮した。いつも喜怒哀楽を全身で表現し「日本サッカーが発展していくためにも、しっかりと組み立て攻撃的に」という姿勢を曲げなかった。
-

-

利き足を「自分の武器」と言えるか J監督の“異次元のボールタッチ”が与えたヒント
2019.03.31川崎フロンターレに技術的な改革をもたらしたのは、前監督の風間八宏(名古屋グランパス監督)だった。 茨城県つくば市で生まれ育った高崎康嗣は、筑波大時代の風間のボールタッチを見て驚愕したという。そんな風間が川崎のアカデミーで手本を見せると、ユースの選手たちも同じように目を丸くした。
-

イニエスタが逆足で触るのは5%以下 “点で触る”利き足指導で磨かれた子供たちの感性
2019.03.25川崎フロンターレを率いて、U-12の世界一を決めるダノンネーションズカップに参加した高崎康嗣は、ここでプレーする大半の選手たちが、利き足に自分の最大値を引き出すポイントを持っていることに気づく。逆にサッカーが長く文化として根づく先進国では、子供たちが遊びの中からそれを習得してくるのだと確信した。実際に帰国して気の置けない仲間に、そのことを伝えると、彼らがさまざまなデータの収集に乗り出してくれた。
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)