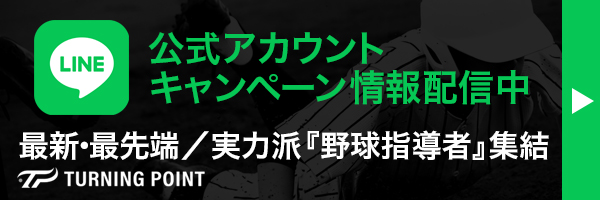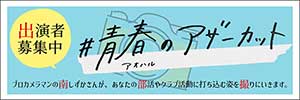続出する中断、1節計18度も…ラグビーも採用した「ビデオ判定」の検証、依存傾向の裏にレフェリーの課題
日本協会のレフェリーOBは危惧「自分が見なくちゃいけないところも見えなくなる」
プレー面やトライシーンは極力自分の目視でのジャッジを奨励する一方で、危険なプレーに関しては積極的にTMOを使うべきだというのがホニス氏の指導方針であり、WRの基本的なスタンスでもある。世界トップクラスのゲームでも、この傾向は確認できる。「6か国対抗」は英国系諸国やフランス、イタリア代表が毎シーズン戦う北半球最高峰の大会だ。今季は現地時間3月15日にフランスの優勝で幕を閉じたが、同8、9日に行われた第4節のTMOを見てみると、3試合で8回導入され半数近い3回がヘッドコンタクトなど危険性を検証するためだった。
【注目】日本最速ランナーが持つ「食」の意識 知識を得たからわかる、脂分摂取は「ストレスにならない」――陸上中長距離・田中希実選手(W-ANS ACADEMYへ)
リーグワンでも同様に危険なコンタクトを見極めるためのTMOは少なくない。8-10節までの3節全18試合をみても、49回のTMOの中で9回、33%は危険なプレーの検証のために行われている。危険回避、抑制が今季のTMO増加の大きな要因なのは間違いないだろう。だが、それを踏まえた上で、レフェリーが1試合平均2.32回のTMOを実施した理由は、かなり複合的だと考えるべきだろう。
TMOに依存しているのではないかという懸念について、日本協会でレフェリー部門の役職も務めてきたOBは、ホニス氏とはまた異なる視点で語っている。
「(依存の傾向は)大きいと思います。今は、誰でも映像を見て細かなシーンも確認出来る。だったらレフェリーもビデオで確認すればいいということです。それはラグビーだけじゃなく、どのスポーツでも同じような事が起きている。他の競技では、映像で判定がでるのならそこは審判が触らなくていいという方向もある。そうなると、段々と映像に依存してしまう。自分が見なくちゃいけないところも見えなくなる」
テクノロジーの進化もあり、観客も含めた誰もがビデオ映像をどこでも容易に、現在進行形で見られる時代だ。このような環境の中で、レフェリーにも目視で不確かな状況があれば、映像で詳細に記録されているのならそれを参考にするべきだという心理状態になるのは難しくない。判定が難しい際どいプレーについては、TMOの介入の有無にかかわらず試合中、試合後にチーム側からの意見や問い合わせは少なくないという。
「海外のリーグ、チームがどれくらいかは分からないが、日本ではチームからアピールしてくるケースも多い。試合中でも、選手がTMOの時にレフェリーがするジェスチャーをしてアピールするシーンが多く見られます。そういうことがあると、レフェリーはTMOをやらざるを得ない、言われたのならやるしかないと考えてしまうケースもあるのです。試合後でも、後付けでチーム側から言ってこられるのなら(その場でTMOを)やってしまった方がいいというのが、今のレフェリーの感覚だと思います」
レフェリーは選手やチームの主張に左右されることなく、厳正、公正に笛を吹く“神聖にして侵すべからず”の存在ではある一方で、このOBの言葉からは、実際の現場では建前だけでは済まない状況が起きていることが判る。レフェリーが、自分自身の判断で好き好んでTMOに依存してしまっているのではない現実もピッチの上にはある。このようなレフェリー以外の要因も、TMOを増やすことに繋がっているのは明らかだ。
後編では、先ず選手のプレー傾向が引き起こすTMO増加の要因から検証する。
(吉田 宏 / Hiroshi Yoshida)
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)