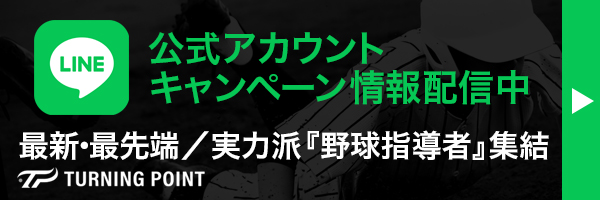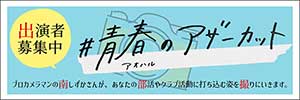秩父宮ラグビー場の客席に“異変” あるリーグワンチームの試み、「南スタンド最前列を…」迎える特別な「3.30」
「誰かのために」だけではなく「自分がどう変容出来るか」
いまやリーグワンに参入する多くのチームが障害者支援に取り組んでいる。BR東京だけが特別ではない。だが、冒頭に紹介した車椅子席の拡大を挙げれば、一見すると単なる座席増設のように見えるが、JRC(日本スポーツ振興センター)が管理・保有するこの施設で、従来の規約、規制を変えることは取材経験上相当な困難が伴うものだ。「前例がない」という一言で終わってしまうことも十分にあり得る中で、今回のような理解、承認を得たことは画期的でもある。
【注目】日本最速ランナーが持つ「食」の意識 知識を得たからわかる、脂分摂取は「ストレスにならない」――陸上中長距離・田中希実選手(W-ANS ACADEMYへ)
そして、BR東京のユニバーサルデー開催への様々な取り組み、背景にある理念を聞く中で、改めて気付かされたことがある。野田広報のこんな話が、まさにその気付きを物語っている。
「これは私個人の思いですが、このイベントを成功させるためには絶対協力してもらわないといけないのが、いわゆる健常者、つまり来場する大多数のファンの皆さんだと思っているんです。私たちだけでこういうことをやりたいと一方的に言えば、それは(障害者を)特別扱いしているだけとネガティブに受け止められてしまうかも知れない。そうじゃなくて、やはりリスペクトというラグビーの文化を持って、皆でユニバーサルデーを作り上げていきましょうと、来場者を巻き込みたいという思いがすごくあるんです。それは、今のブラックラムズのファンの人たちだったら絶対に出来るはずと信じているのですが、私たちとしても取り組んでいきたいのです。オールドファンとか、にわかファンとかありますけど、そういうのじゃないよねという所も込みでユニバーサルかなと思っているのです」
“オールド×にわか論争”はとにかく、ユニバーサルデーが実現しようとする「共通さ」「普遍性」というのは、ハンデキャップを持つ人たちのために様々な不都合さという障壁を取り除くことよりも、むしろ我々大多数の健常者側が、自分たちの一方的な都合だけによる常識や、一般論で障害者をステレオタイプに型にはめて見てしまう一種の偏見というバリアを取り払って、目の前の生身の“仲間”と向き合うことに向けられていることだ。障壁を作ってしまうのは、ハンデキャップがないはずの我々のほうだと考えるべきだろう。
「誰かのために」だけではなく「自分がどう変容出来るか」。3月30日が、そんな一日になれば、健常者、障害者などという境界がさらにシームレスな社会へと1歩近づくことになる。
(吉田 宏 / Hiroshi Yoshida)
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)