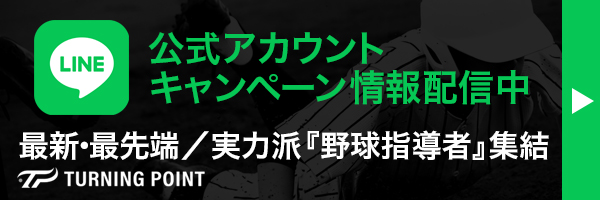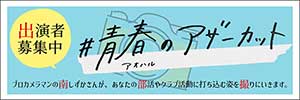続出する中断、1節計18度も…ラグビーも採用した「ビデオ判定」の検証、依存傾向の裏にレフェリーの課題
印象的だった第10節のある試合での開始直後のTMO
では、何故増えているのか。
【注目】日本最速ランナーが持つ「食」の意識 知識を得たからわかる、脂分摂取は「ストレスにならない」――陸上中長距離・田中希実選手(W-ANS ACADEMYへ)
象徴的だったのは、第10節のある試合での開始直後のTMOだろう。攻撃側チームが相手ゴールライン(トライライン)右隅にトライしたと思われたが、結果的にビデオを確認してトライ前にボールを持った選手がタッチラインを踏んだという裁定でノートライとなっている。だが、そのタッチを踏んだシーンは、ARが後方から至近距離のライン際で見ていながら、結果的にTMOでのチェックが導入されている。
誤解してほしくないのは、現状および今回のコラムで個々のレフェリーを糾弾するつもりは毛頭ないことだ。多くの若い日本人レフェリーが、世界レベルのテストマッチで笛を吹こうと自己研鑽に挑んでいる。そして、リーグワンでのTMOを見ていると、レフェリー、TMO担当者らが、より精密に、詳細にプレーを検証しようという、いい意味で生真面目な国民性も反映されているようにも見える。その一方で、例に挙げた試合も含め今季のリーグを取材する中で強く感じるのは、レフェリー、ARが、選択肢として勇気と自信を持って自分自身の目視でジャッジをすることよりも、TMOに委ねるほうが確実だという空気感に包まれていないかという懸念だ。
TMOが国内リーグで採用された直後にも、このような“依存”が高まるのではないかという危惧はあった。取材をすると、レフェリー部門上層部では個々のレフェリーに対して、自分自身がしっかりとプレーを見極めて、自分の判断によるジャッジを尊重するようにアドバイスしていると説明を受けた。ホニス氏は、そのような考え方は現在でも変わらないという。
「日本のレフェリーに伝えている最大のポイントは、より高いワークレートを見せることです。それが自分たち自身でジャッジすることにも繋がるからです。特にトライに関してはテクノロジーに頼ることをあまりせずに、自分たちで判断する。それをするために、自分自身で(プレーを見極めるための)ベストポジションにいられるようにしなければいけないと常々アドバイスしています」
レフェリーはTMOへの依存をし過ぎずに、自分でジャッジをするべきだというのは、ラグビー協会自体も求めている指針なのは間違いない。日本協会では、土田雅人会長が今後の大きな活動目標として男女W杯の開催を掲げ、そのためには代表強化に加えてトップレベルの国際試合も吹けるようなレフェリーの育成を重要ポイントと明言している。日本人レフェリーが世界クラスの国際試合を担うレベルに成長するためには、ホニス氏も指摘する自分の目視、判断力で笛を吹くことは重要な資質だろう。
日本人レフェリーの育成のために招かれたホニス氏は、TMOへの依存傾向という懸念についてはこんな見解も話している。
「先ずはフィールド上にいる3人、つまりレフェリーとARでジャッジしていこうというのが基本ですが、3人で話し合った上で100%の自信を持てない場合はTMOのジャッジを仰ぐこともあります(最終判定はレフェリー)。また、TMOなしでトライが認められた場合でも、細かな部分で見落としがないかをTMO担当者側がコンバージョン(トライ後のゴールキック)の時間等を使い映像をチェックしてレフェリーにTMOの実施を進言するケースもある。そういう理由も含めてTMOが増えているように見えたり、回数が多くなっているのかも知れない。TMOが介入した回数は、確かに昨季より多いのかなとも思いますが、何故実施されたのかという傾向と試合全体をみた時のバランスとしては、そう悪くない(多くない)と思います」
依存というよりも、試合中にレフェリーがTMOを採用してしまう、介入させざるを得ない環境、状況が増えてしまっていることが増加に繋がっているというのがホニス氏の考え方だ。そして、その大きな要因の一つが「安全」なのは間違いない。再びホニス氏の言葉だ。
「ファウルプレーについては、コリジョン(衝突)の際の接点がレフェリー自身で見えないことはよくあることです。そこは、選手への危険性という観点から、用意されたテクノロジーを使って、あらゆる情報を集めてより正確な判断をするように話しています。それでもご指摘の通り、レフェリーというのはテクノロジーに頼るのは最低限にして、いい判断を自分でするべきだというのが大意なのです」
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)