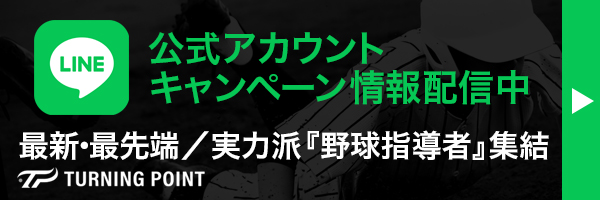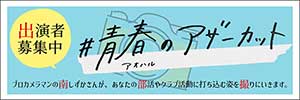創設4年目、変わるリーグワンの現在地 新システム導入で変化…今季はワンサイド減、今後はカタカナ選手増?
「カタカナ選手が増える」の指摘にリーグ関係者はどんな見解?
規約変更により、留学生選手は卒業と同時にカテゴリA選手としてプレー出来ることになっている。実際にBL東京でも、新加入の留学生ら4人が新たにカテゴリA資格を獲得しているが、ハードルが12か月短縮され、継続居住ではなくチームとの契約が条件となれば、4年をクリアした選手の商品価値は跳ね上がることになる。雇用者であるチーム側でも入団即カテゴリAとなる留学生はもちろん、契約から4年待てば日本選手と同等の条件で起用できるメリットを感じて、外国籍選手の採用を増やす可能性は十分にある。
【注目】日本最速ランナーが持つ「食」の意識 知識を得たからわかる、脂分摂取は「ストレスにならない」――陸上中長距離・田中希実選手(W-ANS ACADEMYへ)
現時点では、この変更による日本人選手の雇用に深刻な影響までは至っていないが、もし門戸が狭められることがあれば深刻な問題だ。日本人、外国人の比率や人数が何人ならいいというような議論ではなく、リーグワンでどこまで日本選手の雇用機会やプレー時間を創り出せるかは、代表強化も踏まえて真剣に考えていかなければいけない。肌の色やパスポートで選手をカテゴライズすること自体、議論のある時代だが、将来は日本代表、リーグワンでプレーしたいと憧れ、日本の小中高でラグビーに打ち込む子供たちの数が現状から更に減少するようなことがあれば、競技人口、ファン人口という面で日本ラグビーの将来を支える地盤を揺るがす深刻な事態を招きかねない。
リーグワン関係者は、現行のカテゴリA枠の評価、星野プロデューサーの「カタカナ選手が増える」という指摘に、こう見解を語っている。
「カテゴリ制は日本代表に寄与するという役割では、一定の効果を出してきていると考えています。そして、日本選手と外国籍選手のバランスについては、チームからも様々な意見が上がってきています。リーグ側でも、まだ仮称の段階ですが『普及育成枠』を今後導入して、日本で育った選手らが活躍出来る枠を使って(偏りを)解消していくことを考えています。この枠は、現状の、とりあえず4年いればいいだろうという部分が制限されることを意味しています」
コメントにある「普及育成枠」というのは、2シーズン後(2026-27年)に実施を目指す規定で、カテゴリA選手の一定数を【義務教育期間のうち一定期間を日本で過ごした選手】とすると説明されている。噛み砕けば、カテゴリA内に日本で生まれ育った選手に優遇枠を設けることになる。だが、一部関係者からは「本当に2年後に有効性のある新たな規約が作れるのか、導入出来るのかは不透明」という声もある。日本人、外国人という単純な線引きだけではなく、海外出身の選手が日本国籍を取得すれば、憲法上その選手の雇用の権利に一公益法人がどこまで制約を設けられるかなどの細かな規約の整備も、2シーズン後の導入へ向けて求められることになる。
チーム周辺でも、カテゴリ制にまつわる不満や疑問の声は少なくない。一例を挙げれば、エージェントの問題だ。以前の本コラムでもエージェントについてスポットを当てたが、例えば留学生については、チーム関係者からこんな話を聞いている。留学生が大学3年生、4年生になると徐にエージェントと契約を結び、リーグワン等企業チームとの契約締結時には、チーム側がエージェントに手数料を支払うケースが増えている。ある大学指導者は、「本来、入学(来日)時から生活面も含めて選手の面倒を見て、企業から誘われるまでに育てたのは大学チーム。突然入り込んできたエージェントが10%の報酬を持っていくのに違和感がある」と語る。雇用するチーム側でも「本当に長年に渡り選手をサポートしてきたエージェントならやむを得ないが、現状をみると10%のお金(手数料)を受け取る資格があるのは大学チームのようにみえる」と指摘する。
確かに入団交渉等の詳細な契約や法的な手続きなど、エージェントの役割は選手、チーム双方にとって重要だが、統括組織であるリーグ側、ラグビー協会側が、エージェントと選手、チーム間にしっかりとした規約や枠組みを作る必要があるだろう。本来はエージェントが介入しないはずの日本人選手も含めた大学生についての契約は、野放しになる恐れを孕んでいる。
このような問題は、今回のコラムの“序盤戦の振り返り”というテーマからは離れた議論ではあるが、新カテゴリ制が導入されたシーズンだからこそ、敢えて取り上げた。チーム、リーグ、協会がコミュニケーションを深めながら、現状での課題、改善点を共有して、迅速に対策を講じていい問題だろう。
今季の混戦模様についてグラウンド内外の様々な角度から考えてきたが、後編では引き続きリーグが導入した新規約や、序盤戦の観客動員、さらには新たに導入されたテクノロジーについて検証する。
(吉田 宏 / Hiroshi Yoshida)
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)