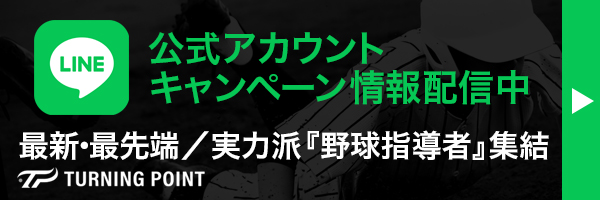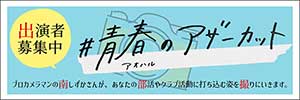創設4年目、変わるリーグワンの現在地 新システム導入で変化…今季はワンサイド減、今後はカタカナ選手増?
カテゴリ制の大きな規定変更はリーグにどう影響?
リーグの変動については、チーム個々の進化に加えて、リーグワンの規約変更という側面からも考える必要がありそうだ。今季開幕を前に、リーグワンでは選手起用・登録におけるカテゴリ制と呼ばれる規定を大きく変更している。特に「カテゴリA」については、チームの戦力に大きな影響を及ぼす可能性がある。
まず「カテゴリ制」について確認しておこう。リーグワンでは発足時から日本国籍選手、外国籍選手の契約、登録の規定として、この制度を導入している。選手を国籍や代表歴などでカテゴリA、B、Cに分けて、それぞれの出場枠、登録枠を設けている。現行の規定は下記の通りだ。
▼リーグワン選手契約および登録に関する規定(カテゴリ制度)
| チーム登録 | 試合登録(23人) | 出場可能人数 | |
|---|---|---|---|
| A日本代表/代表資格保持 | 80%以上 | 17人以上 | 11人以上 |
| B日本代表資格獲得見込み | BC計10人以下 | 任意 | 任意 |
| C他国代表歴/A、B規定外 | 3人以下 | 3人以下 | 任意 |
カテゴリAは日本国籍所有選手および日本代表資格を持つ外国人選手で、リーグの登録選手の大半を占める。Bは将来的にAになる資格を持つ外国人選手、Cは日本以外の代表経験者が主な対象だ。カテゴリAの外国籍選手については、統括団体ワールドラグビー(WR)が定める外国人選手の代表資格に準じているため、昨季までは当該国(日本)での“継続的な居住”が60か月を超えた外国籍選手が認定されていた。継続的というのは、当該国以外での滞在が62日以内とされていた。
この制度の主な狙いは、外国人選手が海外から大量に流入する中で、日本選手の出場や雇用を確保することだった。しかし、今季はそのカテゴリ制に大きな変更があった。WRが昨年8月から代表資格を「継続的な60か月間の居住」から「60か月間当該国のラグビー団体にのみ登録」に変更。これにより、日本のチームで60か月契約を継続していれば、居住時間を問わずに日本代表資格を得られることになった。それに応じて、リーグワンでも今季からカテゴリAの条件を「居住」から「契約」に変更したのだが、更に独自の規約として60か月の契約期間を48か月に短縮している。従来は5年の継続居住が条件だったカテゴリA外国籍選手が、今季から4年間の日本チームとの契約で、日本選手と同じ扱いでプレー出来ることになったのだ。
この変更が、リーグワンのメンバー起用、チーム編成に影響を及ぼし、外国人選手との契約にも変化をもたらす可能性はかなり高い。実際に今季のカテゴリA選手の人数には変化が読み取れる。リーグワンが集計した1月24日時点でのカテゴリAの日本国籍、外国籍選手数を紹介しておこう。
【国籍別カテゴリA選手人数】
| 24-25年 | 23-24年 | |
|---|---|---|
| 日本国籍選手 | ※1060 | 978 |
| 外国籍選手 | ※160 | 106 |
※はリーグ側が1月24日現在で国籍取得状況が未確認のための概算だが、昨季比で日本国籍選手が8%程度の増加なのに対して外国籍選手は60%を超えている。当然のことながら、全カテゴリA選手中の日本国籍選手を見ても、人数は増えてはいるものの比率では昨季の90.2%から86%前後に減少している。
増加した外国籍選手全てが「48か月」「契約期間」を理由にカテゴリA資格を得たわけではないが、規定変更の影響は間違いなくあるはずだ。この変更について、先のBL東京・星野プロデューサーはチーム側のメリット、デメリットをこう指摘する。
「メリットはパフォーマンスの素晴らしい外国人選手を、より多く採用出来ることです。それで競技レベルも上がれば人気も上がってくる。デメリットは、お金の部分と日本人選手の部分。つまり日本選手がプレー出来なくなるのではないかというところです。そこはリーグも、新たな規約を考えています。そういうセットで改革をやればいいとは思います。ただ、確かにこの2年間くらいはカタカナの選手が多くなってしまう可能性はあるでしょう」
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)