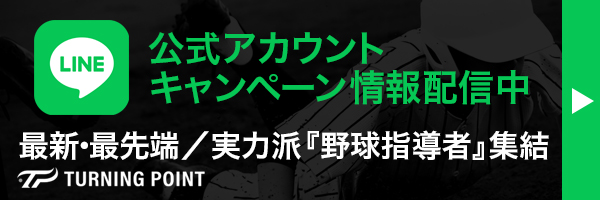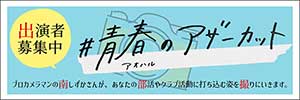指導論の記事一覧
-

「早稲田に勝ちたい」 母校のブランド力を実感、城西大・櫛部静二監督が挑む箱根駅伝での下剋上
2023.12.23今年度の大学駅伝シーズンも佳境を迎え、毎年1月2日と3日に行われる正月の風物詩、箱根駅伝の開催が近づいている。前回大会王者で今季も10月の出雲駅伝、11月の全日本大学駅伝を制し、史上初の2年連続3冠を狙う駒澤大を止めるのはどこか――。「THE ANSWER」では、勢いに乗る“ダークホース校”の監督に注目。今回は2001年の創部からコーチとして関わり、09年から城西大学男子駅伝部を率いる櫛部静二監督に話を聞いた。近年の大学駅伝で熾烈を極めているのが、高校生ランナーのスカウトだ。多くの強豪大学が専任のスタッフを用意して全国を飛び回るなど、競争が激化している。城西大もそうした大学の1つだが、櫛部監督は母校の早稲田大などブランド力で勝る名門の力を感じつつも、「駅伝だけではない」育成の魅力を高校生に伝え勧誘している。(取材・文=佐藤 俊)
-

高校サッカー選手権は「選手のためにある」 ボトムアップ部活で2年ぶり全国、堀越監督が貫く信念
2023.12.22日本のスポーツ界で「選手主体」の指導の大切さが叫ばれる中、育成と結果を両立させているチームの1つが、堀越高校サッカー部だ。11年前、佐藤実監督がボトムアップ型の指導を導入すると、2020年度の全国高校サッカー選手権に29年ぶりの出場。21年度大会にも2年連続で出場すると、今年度も2年ぶりの全国行きを決めるなど、着実に選手主体の指導の質を高めている。今年度については当初、佐藤監督は「難しい年代になる」と見ていたが、選手たちは予想を上回る成長を見せ、全国行きの切符を勝ち獲った。(取材・文=加部 究)
-

低酸素トレを「理解してもらえなかった」 城西大駅伝監督が導入、転機になった1人の選手の挑戦
2023.12.21今年度の大学駅伝シーズンも佳境を迎え、毎年1月2日と3日に行われる正月の風物詩、箱根駅伝の開催が近づいている。前回大会王者で今季も10月の出雲駅伝、11月の全日本大学駅伝を制し、史上初の2年連続3冠を狙う駒澤大を止めるのはどこか――。「THE ANSWER」では、勢いに乗る“ダークホース校”の監督に注目。今回は2001年の創部からコーチとして関わり、09年から城西大学男子駅伝部を率いる櫛部静二監督に話を聞いた。新興校として短期間で結果を残している背景の1つにあるのが、櫛部監督が積極的に取り組む科学的トレーニングだ。中でも低酸素室は他大学より早く取り入れており、実際に効果も出ていることから選手も意欲的に取り組んでいるという。(取材・文=佐藤 俊)
-
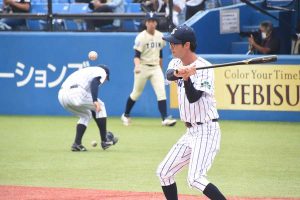
部員200人超、コンバート活発 高校野球とは違う大学野球指導の面白み、選手が「なぜ?」問い返す
2023.12.20仙台大教員で、2018年から硬式野球部で野手を中心に指導している小野寺和也コーチ(36歳)。今秋のドラフトで中日ドラゴンズから3位指名を受け、仙台大の野手で初の支配下指名を勝ち取った辻本倫太郎内野手(4年・北海)をはじめ、数多くの現役部員やOBが慕う敏腕コーチだ。大学野球の指導者として抱く信念と葛藤を深掘りした。(取材・文=川浪 康太郎)
-

東北からNPB選手を次々育てる「小野寺さん」とは 中日ドラ3ら輩出、原点は慶大のBチーム降格で訪れた転機
2023.12.20みちのくの大学球界に、的確な指導で次々と選手の才能を開花させている指導者がいる。仙台大教員で、2018年から硬式野球部で野手を中心に指導している小野寺和也コーチ(36歳)のことだ。「小野寺さんのおかげで」「小野寺さんのアドバイスで」――。仙台大硬式野球部の野手陣を取材すると、必ずと言っていいほど「小野寺さん」の名前が挙がる。そんな若きコーチの指導者としての原点は、東京六大学野球リーグ戦で二度の首位打者に輝いた慶應義塾大時代にあった。(取材・文=川浪 康太郎)
-

「箱根がすべてではない」 城西大・櫛部静二監督、駅伝指導の根底にあるトップ選手育成の夢
2023.12.19今年度の大学駅伝シーズンも佳境を迎え、毎年1月2日と3日に行われる正月の風物詩、箱根駅伝の開催が近づいている。前回大会王者で今季も10月の出雲駅伝、11月の全日本大学駅伝を制し、史上初の2年連続3冠を狙う駒澤大を止めるのはどこか――。「THE ANSWER」では、勢いに乗る“ダークホース校”の監督に注目。今回は2001年の創部からコーチとして関わり、09年から城西大学男子駅伝部を率いる櫛部静二監督に話を聞いた。第2回のテーマは、現役時代と現在のトレーニング理論の違いについて。自ら学び、アップデートしながら選手を指導しているという櫛部監督。視線の先には箱根駅伝だけでなく、世界と渡り合えるランナーを育成したいという強い思いがあった。(取材・文=佐藤 俊)
-

箱根駅伝で栄光と挫折を経験 城西大・櫛部静二監督、寄り添う指導の裏にある「引きずった」過去
2023.12.17今年度の大学駅伝シーズンも佳境を迎え、毎年1月2日と3日に行われる正月の風物詩、箱根駅伝の開催が近づいている。前回大会王者で今季も10月の出雲駅伝、11月の全日本大学駅伝を制し、史上初の2年連続3冠を狙う駒澤大を止めるのはどこか――。「THE ANSWER」では、勢いに乗る“ダークホース校”の監督に注目。今回は2001年の創部からコーチとして関わり、09年から城西大学男子駅伝部を率いる櫛部静二監督に話を聞いた。自身も現役時代に箱根駅伝を4度走り、栄光と挫折を味わった。新興校を率いて15年目、着実に実績を積み上げる中で、そうした経験が選手への指導に生かされているという。(取材・文=佐藤 俊)
-

「山の神」柏原竜二を支えたデータに基づく指導 東洋大・酒井俊幸監督が個性を尊重する理由
2023.12.07箱根駅伝の常連校で通算4回の優勝を誇る東洋大学陸上競技部は、「その1秒をけずりだせ」をスローガンに個々の才能を磨く指導で多くの日本を代表するランナーを生み出してきた。そんな名門の長距離部門を2009年から率いて以来、箱根駅伝で総合優勝3回、14年連続シード権獲得に導いているのが、就任15年目を迎えた酒井俊幸監督だ。47歳にして、すでに名将の風格を漂わせる指揮官のコーチング哲学に迫るインタビュー。日本を代表する多くの名ランナーを育てた酒井監督だが、特筆すべきは大学卒業後の成長度だ。その背景には1人ひとりの個性を尊重する、データに基づく合理性があった。(取材・文=牧野 豊)
-

「箱根駅伝の捉え方も変わってきている」 東洋大・酒井俊幸監督が大切にし続ける“その先”の世界
2023.12.06箱根駅伝の常連校で通算4回の優勝を誇る東洋大学陸上競技部は、「その1秒をけずりだせ」をスローガンに個々の才能を磨く指導で多くの日本を代表するランナーを生み出してきた。そんな名門の長距離部門を2009年から率いて以来、箱根駅伝で総合優勝3回、14年連続シード権獲得に導いているのが、就任15年目を迎えた酒井俊幸監督だ。47歳にして、すでに名将の風格を漂わせる指揮官のコーチング哲学に迫るインタビュー。前編では、酒井監督が大学生を指導する上で就任当初から変わらずに大切にしていることや、箱根駅伝に抱く思いに迫った。(取材・文=牧野 豊)
-

ガーナ人の父を持つ日本人 境遇に悩まないボクサー岡澤セオンの「何に目を向けるか」という生き方
2023.11.18アマチュアボクシングの2021年世界選手権男子ウェルター級(67キロ以下)金メダルの岡澤セオン(INSPA)が、「THE ANSWER」のインタビューに応じた。アマアスリートながら、自らかき集めたスポンサー収入で活動する27歳。アマ初の「プロのアマチュアボクサー」として2021年東京五輪にも出場した。
-

大学指導者が失ってはいけない視点とは? 青学大・原晋監督が箱根駅伝「全国化」を訴え続ける理由
2023.11.07自主性や主体性のある選手を育てるために、指導者にはどのような能力が求められているのか。2004年から青山学院大学駅伝部を率い、箱根駅伝で6回の優勝に導いた原晋監督が、10月19日に行われた一般社団法人大学スポーツ協会(UNIVAS)、株式会社マイナビが運営するアスリート向けキャリア支援サービス『マイナビアスリートキャリア』、株式会社SPLYZAの共催で実施されたトークセッション「選手の自主性や主体性を活かすための指導者の在り方とは」に登壇。UNIVAS理事で立命館学園副総長・立命館大学副学長の伊坂忠夫氏らとともに、現代のあるべきスポーツ指導者の姿について語り合った。
-

歴代主将やマネジャーらが卒業後も社会で活躍 青山学院大・原晋監督が貫く「未来志向」の人材育成
2023.11.06昨今のスポーツ界で話題となっている選手の主体性を尊重する指導法は、アスリートの成長にどのような影響を与えるのか。2004年から青山学院大学駅伝部を率い、箱根駅伝で6回の優勝に導いた原晋監督が、10月19日に行われた一般社団法人大学スポーツ協会(UNIVAS)、株式会社マイナビが運営するアスリート向けキャリア支援サービス『マイナビアスリートキャリア』、株式会社SPLYZAの共催で実施されたトークセッション「選手の自主性や主体性を活かすための指導者の在り方とは」に登壇。UNIVAS理事で立命館学園副総長・立命館学園副学長の伊坂忠夫氏らとともに、現代のあるべきスポーツ指導者の姿について語り合った。
-

箱根駅伝優勝6回、青山学院大・原晋監督と“選手主体”の指導論 20年前は「むしろ君臨型だった」
2023.11.05一般社団法人大学スポーツ協会(UNIVAS)は、10月19日に株式会社マイナビが運営するアスリート向けキャリア支援サービス『マイナビアスリートキャリア』と株式会社SPLYZAとの共催で、「選手の自主性や主体性を活かすための指導者の在り方とは」をテーマにしたトークセッションを都内で開催した。昨今のスポーツ界では様々なスタイルの指導法が確立されているが、選手の主体性を尊重することはアスリートにどんな影響を与えるのか。このトークセッションに、UNIVAS理事で立命館学園副総長・立命館学園副学長の伊坂忠夫氏らとともに特別ゲストとして登壇したのが、青山学院大学駅伝部を率いる原晋監督だ。
-

圧倒的多数の「敗者」がサッカー文化を支える 日本の育成年代で選手に伝えるべき3つのバランス
2023.09.24サッカー日本代表は2022年カタール・ワールドカップ(W杯)で2大会連続ベスト16に進出し、メンバーの大半が今や欧州でプレーする時代となっている。一方で日本人指導者が海外で結果を残すのは容易なことではないが、そうした中で大きな足跡を残しているのが、セルビア代表コーチとしてカタールW杯の舞台に立った喜熨斗勝史(きのし・かつひと)氏だ。2008年から名古屋グランパスでドラガン・ストイコビッチ監督の信頼を勝ち取ると、15年から中国の広州富力に、21年からセルビア代表にコーチとして呼ばれ、指揮官の右腕となっている。
-

「整いすぎた環境」はマイナスに働く ドイツ人指導者が説く、子供の成長を促す“向き合い方”とは
2023.09.09ドイツサッカー連盟公認A級ライセンスを持ち、20年以上にわたって現地で育成年代の選手を指導してきた中野吉之伴氏が、「THE ANSWER」に寄稿する不定期連載「サッカーと子育て論」。ドイツで子供たちを日々指導するからこそ見える、日本のスポーツ文化や育成年代の環境、子育てに対する考え方の違いなどについて迫る。今回はドイツの指導者講習会で知り合った盟友で、プレミアリーグでの監督経験もあるヤン・ジーベルト氏の言葉から、子供たちの成長につながる指導者側の最適なアプローチに迫っている。
-

原辰徳監督から受けた「人としての教育」 巨人で裏方を経験、荻原満が学生に伝える一流の教え
2023.08.31今年から東北工業大硬式野球部のヘッドコーチ(HC)に就任した荻原満氏(57歳)。仙台商高、東海大を経て巨人に入団し、1988年から92年まで投手として5年間プレーした。現役引退後も巨人に残り、打撃投手やマネージャーを歴任。荻原氏は「プロの世界で選手、裏方を経験したからこそ、今こうやって教えられる」と胸を張る。後編では、その濃密な野球人生に迫る。(取材・文=川浪 康太郎)
-

巨人で選手&裏方20年 東北工業大・荻原満HC、最下位チームを変えた「一方通行ではない」指導
2023.08.28仙台市内にある東北工業大硬式野球部のグラウンドには、ストップウォッチ片手に大きな声で指示を出すヘッドコーチ(HC)の姿がある。プロ野球・巨人でプレーした経歴を持つ荻原満氏(57歳)だ。東北工業大はリーグ戦で春秋ともに最下位(春は宮城教育大と同率)に沈んだ昨年から一転、今春のリーグ戦では4勝を挙げて4位、新人戦は仙台大を破って準優勝と躍進。今年から就任した指揮官の「改革」は着々と進んでいる。前編では崩壊しかけていたチームを立て直した指導法について話を聞いた。(取材・文=川浪 康太郎)
-

現役時代の実績で「監督が務まる時代ではない」 欧州事情を知る日本人「サッカーの形が変わった」
2023.08.24サッカーの母国であるイングランドは、隆盛を極めるプレミアリーグを筆頭に長い歴史によって築かれた重厚な文化や伝統があり、いつの時代も圧倒的な権威を保っている。そんな世界最高峰の舞台に乗り込み、アジア人として初めて2018年にイングランドサッカー協会(FA) 及び欧州サッカー連盟(UEFA)公認プロライセンスを取得したのが高野剛氏だ。インタビュー最終回は、現在在籍するシント=トロイデンでの育成の仕事について話を聞きながら、監督に求められる資質について持論を展開した。(取材・文=加部 究)
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)