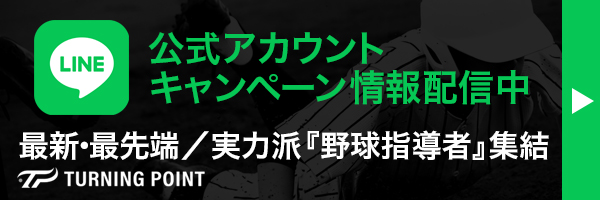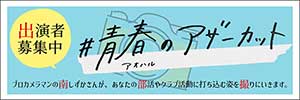指導論の記事一覧
-

C.ロナウドもベイルもこう蹴っている 異色の指導者が極めた“ふかせない”シュート
2018.11.23欧州のトップシーンとJリーグを比べて最も残念なのが、ゴール前の引き締まった攻防の頻度ではないだろうか。欧州ならバイタルエリア(ペナルティーエリア手前のDFとMFライン間のスペース)で少しでも隙ができれば、攻撃側は躊躇なくシュートを打つ。そして確信に満ちた抑えの効いたシュートを、GKが素晴らしい反応で弾き出す。そんなシーンが頻発するから、スタンドも自然と熱気を帯びていく。
-

「こんなに怒ったジーコは初めてだった」 “常勝軍団”鹿島を生んだ25年前の大敗
2018.11.08AFCチャンピオンズリーグ決勝の第1戦に2-0で勝利し、通算20冠を目前にした鹿島アントラーズだが、やはりクラブに勝ち癖をつけたのはジーコ(現・鹿島テクニカルディレクター)だった。
-

日本スポーツ界が断ち切るべき“負の連鎖” 選手を追い込む「勝利至上主義」と美談
2018.11.02「左足首を故障していたけど、代わりがいないのでピッチに立ち続けた。とても人道的とは言えなかった」――イビチャ・オシム(元日本代表監督)
-

大坂なおみとの絆は「デスノート」から生まれた バイン氏が築いた“信頼のカタチ”
2018.10.24女子テニスのツアー最終戦、WTAファイナル(シンガポール、DAZN独占生中継)の出場権を掴み、初陣を終えた大坂なおみ(日清食品)。コート上では迫力あるショットを炸裂させる大坂だが、一旦試合が終わると、人見知りでシャイな一面が現れてくる。他人に心を許すまでしばらく時間を要するという21歳だが、昨年12月からコーチに就任したサーシャ・バイン氏は早々に信頼関係を築き、秘める才能を開花させた。
-

大坂なおみをいかに覚醒させたのか バイン氏がセリーナと重ねた“勝者の共通点”
2018.10.22今季テニスの全米オープンで初優勝を飾り、世界ランクでも4位に躍進した大坂なおみ(日清食品)。21日に開幕したWTAファイナル(DAZN独占生中継)では、選ばれしトッププレーヤーの頂点に立ち、大きな成長を遂げた1年の締めくくりを目指す。
-

大坂なおみを変えた指導哲学 なぜ、バイン氏は世界1149位から名コーチになれたのか
2018.10.21テニスの全豪オープンで16強進出を果たし、BNPパリバ・オープンではツアー初優勝。大坂なおみ(日清食品)は2018年シーズンを幸先良く滑り出した。そして、日本女子選手初となる全米オープン優勝の快挙達成し、21日開幕のWTAファイナル(DAZN独占生中継)を目前に控える。2016年にはWTAアワード最優秀新人賞に輝き、2017年の全米オープンでは初戦で前年覇者のアンゲリク・ケルバー(ドイツ)に勝利するなど、徐々に頭角を現してはいたが、今季その実力が一気に開花した印象は強いだろう。
-

ジーコが語る「プロとアマの違い」 才能の宝庫ブラジルで貫いた自己管理の大切さ
2018.10.16ジーコが加入したのはJリーグの鹿島アントラーズではない。アマチュア時代の日本リーグ2部の住友金属だった。しかし住友金属は、Jリーグ参戦を目指すからこそ、ジーコを招聘する理由があった。
-

世界的サッカースクールの外国人指導者が断言 子供の指導で最も大切なこととは
2018.09.18「若い選手を教えるには、何より忍耐強さが必要だ。だから短気な私は、指導者を育成する側に回った」――アルフレッド・ガルスティアン(クーバー・コーチング共同創設者)
-

「コピーはオリジナルに敵わない」 エディーHCが語る日本スポーツとジャパンウェイ
2018.09.13近年、日本スポーツは選手の海外進出が積極的に進み、ボーダレス化が目覚ましい。その結果、国際舞台で「日本と世界」を意識する機会が増えている。日本が世界と戦う上で度々、キーワードとして浮上するのは「日本らしさ」だ。「日本らしい野球」「日本らしいバレー」といった表現で使われることをよく耳にする。英語で言えば「ジャパンウェイ」。サッカー日本代表の森保一新監督が就任会見で使っていたフレーズも記憶に新しい。しかし、「スポーツにおける日本らしさ」とは一体、何だろうか。
-

「若い年代こそ最も優秀な指導者が必要」 フランス名将が主張した選手育成の重要性
2018.09.10「若い年代にこそ最も優秀な指導者が必要だ。そんな彼(ジェラール・ウリエ=当時フランス協会技術委員長)の考え方に、私も共鳴した」――アルフレッド・ガルスティアン(クーバー・コーチング共同創設者)
-

1位じゃないとダメなのか 元オリンピック選手と考える「教育の日本らしさと弱点」
2018.09.09神奈川にある小学校が今、脚光を浴びている。LCA国際小学校。日本でも稀な、株式会社が運営する私立校だ。単なるインターナショナルスクール的な学校というわけではない。同校がこだわっているものが、“本物”だ。その一環として、画期的な新たな取り組みが始まった。
-

子供はどう褒めれば伸びるのか 元オリンピック選手と考える“教える”の価値
2018.09.08神奈川にある小学校が今、脚光を浴びている。LCA国際小学校。日本でも稀な、株式会社が運営する私立校だ。単なるインターナショナルスクール的な学校というわけではない。同校がこだわっているものが、“本物”だ。その一環として、画期的な新たな取り組みが始まった。
-

「ミスを怖れない」子供をいかに育てるか 外国人指導者が抱いた日本スポーツの課題
2018.08.31アルフレッド・ガルスティアンは、世界に普及する育成メソッド「クーバー・コーチング」の創始者の一人である。母国イングランドに限らず、フランス、ドイツ、イタリア、ブラジル、米国など、世界を幅広く飛び回り、テクニカルな指導やアドバイスを送っているが、日本にもコンスタントに留まり指導に時間を割いている。フランス協会とも長く良好な関係を続け、アーセン・ベンゲル(アーセナル前監督、名古屋グランパス元監督)とも日本の事情について話すことが少なくないという。
-

日本サッカー屈指の名将と“アメ”の使い方 「悪い時は友だちがいなくなるけど…」
2018.08.23「日本サッカーの父」と呼ばれたデットマール・クラマーは、1964年に開催される東京五輪に向けた代表チーム強化のために、ドイツサッカー連盟(DFB)から特別コーチとして派遣された。クラマーは自他ともに認める厳しい指導者で、日本代表選手の中には時に「赤鬼」と呼ぶ者もいた。
-

「日本はスポーツを楽しむのが難しい国」 ドイツ人指導者が驚いた母国との環境差
2018.08.13「日本は労働時間、通勤時間が長くて、土地が高い。一般人がスポーツを楽しむのが物凄く難しい国。でも歴史は速やかには形成されない。できたことをポジティブに楽観視していってほしい」――ゲルト・エンゲルス(現・ヴィッセル神戸ヘッドコーチ)
-

猛暑で問われる部活のあり方 ボトムアップ理論が実証した「量より質」の重要性
2018.07.31「僕はベンチでコーヒーを飲んでいたら勝っちゃいました」――畑喜美夫(生徒主導で部活を実践する“ボトムアップ理論”の発案者)
-

日本サッカーと“韓国コンプレックス” 「一生勝てない」意識を払拭した名将の教え
2018.07.24「日本には、技術や組織力という韓国とは別の特徴がある。それをオフトは教えてくれたんです」――福田正博(元日本代表FW)
-

育成年代から描く「引退後の人生設計」 25歳校長が目指す“セカンドキャリア教育”
2018.07.01淡路島に新設する通信制学習センターの特徴は、サッカーのエリートを育成するだけではなく、引退後の人生設計にも踏み込んでいるところだ。
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)