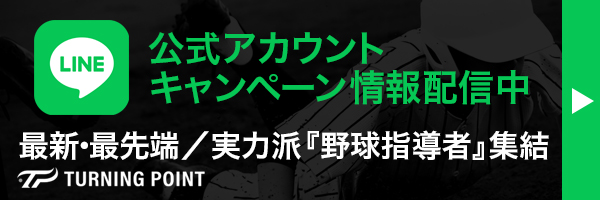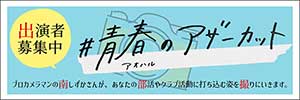高校野球の7回制、選手はこう考える 多摩高が始めた“実践研究”に集まる声…時短にならない場合も

選手も指導者も7回制に「やりきれない思いはどうしても残る」
すでにWBSC(世界野球ソフトボール連盟)が7回制の導入を進めており、高校野球の年代でもU-18の世界大会は7回制になっている。日本国内でも、社会人野球の一部大会で導入が進んでいる。もし高校野球が導入に踏み切れば、その影響力はこれまでの比ではない。
多摩高では昨秋、3度の練習試合を7回制のもとで行ってみた。研究としてはまだ、有効なデータを集めているところだが、相手校の選手にもアンケートを行うなどして、様々な意見を吸い上げている。日照時間が短くなる秋に行ったため「7回制なら2試合できる」と前向きな意見もあったが、現状では戸惑いを訴える声が多いという。
7回制の方が、9回行った場合の平均より試合時間が延びたケースもあった。ピッチクロックの研究にも参加した鈴木諒介(2年)は「点数を取れる機会が減るので、序盤からとにかく点を取られないようにと前進守備を敷く場合もあった」と戦略の変化を指摘。矢川も「丁寧にサインを出すことで、試合時間に影響がある」と、単純な“時短”につながらないという感覚があるという。
それよりも大きな違和感は、やはり「野球=9回」という常識で育ったことによる感情的な割り切れなさだ。矢川は「実際に夏の大会がロースコアで進んで、7回で終わって負けてしまった時、やりきれない思いはどうしても残りますよね」と口にする。現状で集まった声は8割ほどが反対だといい「選手はそこを求めていないということだと思うんです。それより疲労をとる方法、今の5回終了後のクーリングタイムなどを進めていく方がいいのかなと思っています」と、選手の負担軽減には他の道もあると考えている。
同高の飯島佑監督は、さらに指導者の立場から「選手にあげられる出番が減ってしまうのはどうしても気になります。特に夏の大会を考えたときに。うちのような部員が少ないところでもそうなるので、部員が多い学校ではさらに……」という悩みを口にする。高野連は議論を進め、年内に結論を出す方向性だ。
(THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori)
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)