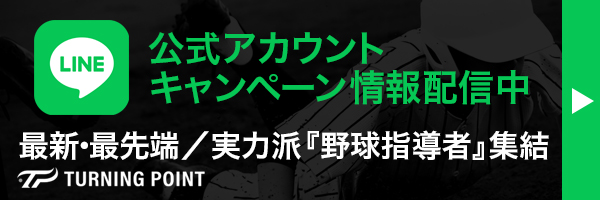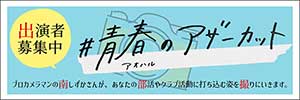高校野球の7回制、選手はこう考える 多摩高が始めた“実践研究”に集まる声…時短にならない場合も
日本高野連は昨夏、高校野球での7回制導入に向けて協議を開始していると明らかにした。特に炎天下で行われる夏の大会が、選手の健康に悪影響を及ぼすとして、試合時間の短縮を目指す動きがある。これに対し「実践研究」を進めている高校生がいる。神奈川有数の進学校・県立多摩高の野球部は、ピッチクロックの導入や7回制といった試合時間短縮法を実際に運用し、データとともに現場の声を集めている。高校野球の現場は、7回制という大変化をどう考えているのだろうか。

神奈川県立多摩高の研究…ピッチクロック&7回制で出た意外な結果
日本高野連は昨夏、高校野球での7回制導入に向けて協議を開始していると明らかにした。特に炎天下で行われる夏の大会が、選手の健康に悪影響を及ぼすとして、試合時間の短縮を目指す動きがある。これに対し「実践研究」を進めている高校生がいる。神奈川有数の進学校・県立多摩高の野球部は、ピッチクロックの導入や7回制といった試合時間短縮法を実際に運用し、データとともに現場の声を集めている。高校野球の現場は、7回制という大変化をどう考えているのだろうか。
多摩高の野球部員は、週1回ほど授業に組み込まれる「総合的な探究の時間」に、野球について様々な角度からの研究を行っている。昨年12月に仙台市で行われた日本野球学会では「高校野球へのピッチクロック導入は試合短縮につながるか」というテーマでのポスター発表を行った。
米大リーグですでに導入されているピッチクロックは、試合時間の短縮が目的だ。高校球児にとっても人ごとではない。気候の変化や、熱が逃げづらい人工芝球場の増加などにより、夏の大会では試合中に足をつって動けなくなり、治療を受ける選手が珍しくない。選手の健康を守るため、高野連はクーリングタイムの導入など様々な策を実行に移しており、試合時間の短縮もこの延長線上にある。
多摩高野球部では、学校のグラウンドに本格的なピッチクロック設備を導入。昨年行った15回の練習試合で、試合時間にどのような変化が表れたかを自校と対戦校に分け、データとして収集した。走者なしのケースは15秒、走者ありで20秒。1回目の違反は投手に警告を与え、2回目からは1ボールをとるというルールで運用した。
すると、1イニングあたりの時間が逆に延びてしまうという驚きの結果が出た。自校も対戦校も同じで、四死球の数が明らかに増えたのだ。発表を担当した矢川聖(2年)は「時間を短縮しようとして行っているのに、真逆の結果が出たことが衝撃でした」と言う。その原因として「高校生のメンタルでは、目立つ位置にタイマーがあることが気になってしまう」と分析した。投手に「焦りを感じたか」と質問すると「とても感じた」「感じた」という答えが過半数を超えたのだ。
投球間隔をルールで短くしても、対戦打者が増えては全体の試合時間が短くならない。そのため現状では「高校野球でのピッチクロック導入は合理的ではない」と結論づけ、発表した。今後も研究を続けていくが、さらに発展させたテーマの準備も進めている。それが話題となっている7回制だ。
![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)